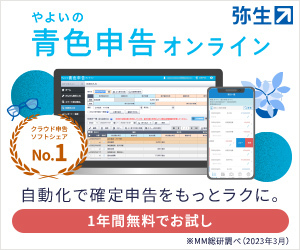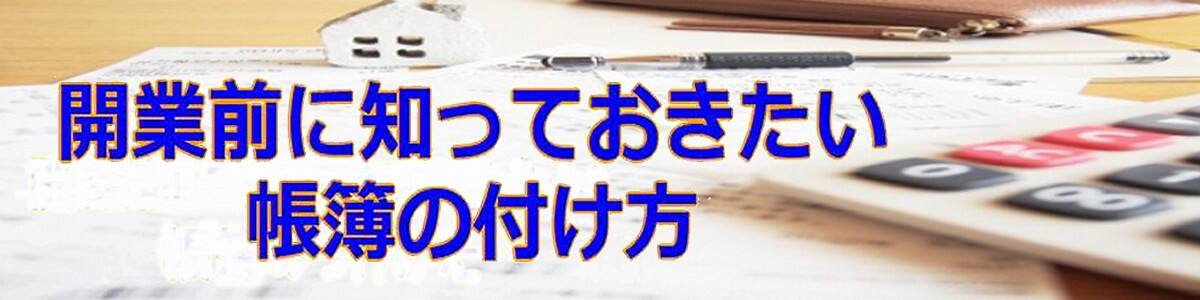
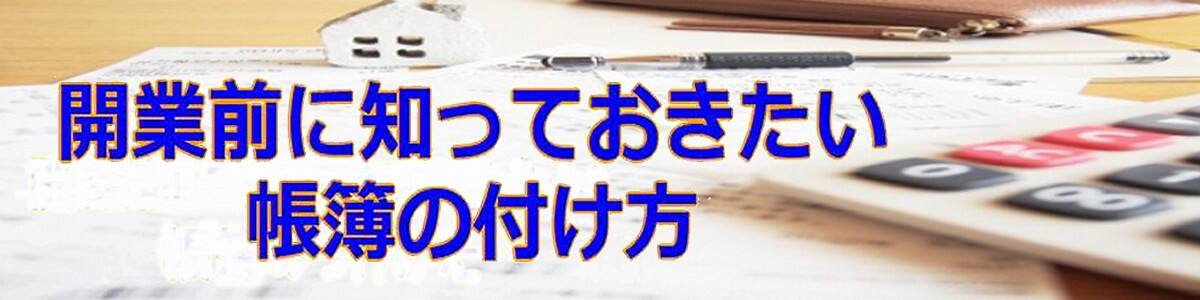
サイト内には、アフィリエイト広告が含まれています。
インボイス制度と電子帳簿保存法を簡単に
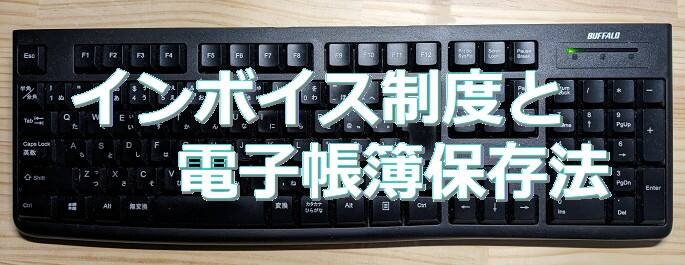
インボイス制度とは、取引において発注者が請求書の内容を電子的に送信・受信することで、取引の効率化やコスト削減を図れる制度です。
具体的には、請求書の発行から支払いまでのプロセスを電子化し、紙媒体からの転記作業や手書きの請求書の作成の手間を省くことができ、請求書の誤りや漏れを事前に発見しやすくすることで、取引の信頼性や精度の向上につながります。
インボイス制度は、一般的にはEDI(Electronic Data Interchange)やXML(Extensible Markup Language)などの電子的なフォーマットを使用し請求書を保管・管理します。ます。
日本では、インボイス制度の適用に関しては、選択的登録制をとっていますが、他国では電子請求が義務化されているところもあります。
インボイス制度登録方法
インボイス制度の登録方法は国や地域によって異なりますが、一般的には以下のような手順があります。
- インボイス制度に参加するためには、登録申請書を提出する必要があります。
登録申請書には、企業情報や参加する取引の内容などが記載されます。 - 導入登録申請書承認後、実際にインボイス制度を導入する前にシステムの動作確認や送信テストなどが必要となります。
- インボイス制度に参加するには、認証を取得する必要があります。
- 利用開始認証を取得した後は、インボイス制度を利用することができます。
利用方法は、登録したシステムを介して請求書を電子的に送信することで行います。
インボイス制度の詳しい利用方法は、国税庁のWebサイトをご覧ください。
日本におけるインボイス登録手順
日本におけるインボイス制度の登録手順について説明します。
- インボイス制度に参加するには、国税庁のWebサイトから登録申請書をダウンロードし、必要事項を記入して提出する必要があります。
- 登録申請書承認後、実際にインボイス制度を導入する前に国税庁によるシステムの動作確認が必要で、確認のために請求書データをテスト送信し、国税庁のシステムと正しく連携できるかを確認します。
- 認証取得には、システムの承認の進行状況や送信されるデータの内容などが審査されます。
- 利用開始認証を取得したら、インボイス制度を利用することができます。
- 利用方法は、登録したシステムを介して請求書を電子的に送信することで行います。
なお、日本のインボイス制度には、「基本インボイス制度」と「発信者責任型インボイス制度」の2つがあります。
参加方法や手続きについては、それぞれ異なるため、詳細は国税庁のWebサイトを確認してください。
因みに、国税庁がインボイス制度の特集ページを公開していますので、そちらのページをご紹介しておきますので、ご確認ください。
「基本インボイス制度」と「発信者責任型インボイス制度」の違い
「基本インボイス制度」と「発信者責任型インボイス制度」の違いは、主に次のようなものになります。
- 「基本インボイス制度」は、請求書の発行義務がある事業者が発行した請求書を電子データで送信することができる制度です。
送信されたデータは、税務署によって受信され、課税対象の取引の税額計算などに使用されます。 - 「発信者責任型インボイス制度」は、請求書受信者に請求書の保存・保管が義務付けられる制度で、送信者は請求書を送信するだけで、受信者に受領後の管理が求められる制度です。
仮に受信者が管理義務を怠った場合、罰則が科される可能性 があります。
以上のように「基本インボイス制度」では送信者が請求書の管理・保存を担当し、
「発信者責任型インボイス制度」では受信者が請求書の管理・保存の役割を担います。
なお、どちらの制度も登録手続きを行う必要があり、詳細については国税庁のWebサイトを確認するようにしてください。
インボイス制度に登録するメリット
インボイス制度に登録するメリットは以下の通りです。
- インボイス制度に登録することで、請求書の発行が簡単になります。
電子データとして送信することで、印刷や郵送の手間を省くことができます。 - インボイス制度に登録することで、請求書の管理を簡単になります。
請求書の発行状況や支払い状況などをシステムで管理することができるので、手作業によるミスを軽減すことができので、確認作業の効率化が図れます。 - 3)決算作業の大幅な削減が可能になります。
インボイス制度に登録しないデメリット
インボイス制度に登録しない場合、次のようなことが発生します。
- インボイス制度に登録していない場合、紙の請求書の発行が必要なり、これまでどおり印刷や郵送などの手間やコストが必要となります。
- 紙の請求書を発行する場合、手作業での請求書管理が必要となり、発行状況や支払い状況などを手動作業で管理しなくてはなりません。
- インボイス制度に登録していない場合、紙の請求書を発行するため、税務申告のための帳簿を作成する必要があるうえ、発行済み請求書の保管・管理が煩雑になります。
- インボイス制度に登録せず紙の請求書を使い続けることで紙の使用量が増え、環境負荷が大きくなります。
以上のように、インボイス制度に登録しない場合、紙の請求書を使い続けることで、手間やコストが増えるだけでなく、環境負荷も増す可能性があるのです。
ここまで書かせていただいてきましたが、今一合点が行きませんので、自分で解決する労力を考えると、今使ってるクラウド会計ソフトを活用するほうが、ずっと簡単ですので、みなさんにもクラウド会計ソフトを活用して、無駄な労力を使うことなく、インボイス制度へ対応されることをお勧めします。
参考までにこちらでご紹介している会計ソフトをまとめたページがございますので、よろしければご覧ください。
国税庁の主張するきれいごとの部分を紹介してきましたが、財務省の本音は消費税の取りっぱぐれを無くして、徴収率をあげるのが目的であることは、誰もが知っていることだと思います。
今回のインボイス制度の肝は、請求書を発行すると国税庁に瞬時に売上が把握されるところにあります。
これにより、国税庁から見た完全なガラス張り取引になり、日本国内のインボイス制度登録事業所全ての取引を一元的に監視する制度が整うことになり、税全般の徴収率は、飛躍的に上ることになるでしょう。
それ自体は、素晴らしい事だと思いますが、であるならば、確定申告をもっと簡素化するくらいの配慮が有って、しかるべきだと私は思います。
こうして考えてくると、最終的には、個人の所得状況や消費動向なども全てマイナンバーと紐付けされるようになって、つつましやかに生活する一般国民は、容赦なく税金を取り立てられる羽目になるのでしょう。
まるで、時代劇に出てくるワンシーンのように、悪代官役の政治家と小物の手下役の財務省官僚が、薄暗い部屋で悪だくみをしてほくそ笑んでる姿が思い浮かびます。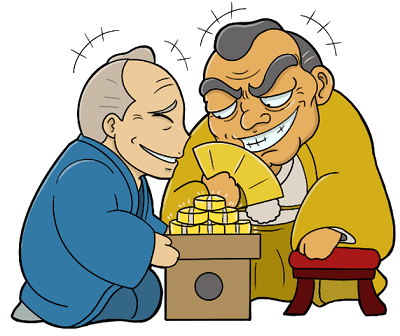
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは、日本国内の企業や個人事業主が、自社で作成した帳簿を保存するための法律で、この法律は、2001年にすでに施行されていますのですでにご存知だと思います。
電子帳簿とは簡単に言ってしまえば、パソコンやスマートフォンなどの電子機器で、取引履歴や経理簿帳などの記録を電子データ化したものを指します。
この電子帳簿を保存することで企業や個人事業主は、税務署などの監査機関からの指導や税務調査に対応することができます。
電子帳簿保存法では、保存するデータの形式や保存期間、保存場所、保存の際の必要な情報付加などが規定されています。
また、保存したデータが改ざんされていないかを確認するための電子署名やタイムスタンプの取り扱いについても定められています。
電子帳簿保存法は、企業や個人事業主が適切に電子帳簿を管理することで、税務関係の帳簿トラブルを未然に防ぐことを目的としています。
電子帳簿保存法に関しての大まかな概要はこんな感じです。
詰まるところ企業にしても個人事業主にせよ、脱税が横行していて、その摘発件数や摘発される脱税額も巨額になってきていて、さらにその資金を使っての贈収賄事件も数多く摘発されているのは、みなさんご存知のところだと思います。
直近では、東京オリンピック関連の高橋治之容疑者が主導したとされる贈収賄事件は記憶に新しいところでしょう。これらの資金の一部も脱税で蓄えられた蓄財が用いられたのではないかと推察されるとこで、脱税が更なる経済犯罪を誘発する温床になっているとの指摘されているので、これらを無くすために施行されたのが、電子帳簿保存法だったのですが、それもすり抜ける手口を考えるやからがこの国には、いかに多いのかが分かります。
こんな不当な輩をのさばらせないためにも厳格に運用することが大切だと思います。
電子帳簿の適切な保存方法
電子帳簿保存法に関しては、施行後すでに20年以上経過していますので、今更語ることもないと思いますし、多くの方が利用されていると思われる、クラウド会計ソフトを使っていれば、何の問題もないのですが、個別に対応しようとする方のために、簡単に電子帳簿としての保存に必要な要件をまとめてご紹介しますので、参考になるかどうか分かりませんが、ご覧ください。
- 電子帳簿はデータの紛失や破損を防ぐために、適切な保存場所に保管する必要があり、安全で且つアクセスしやすく、災害に強い場所を選定することが重要です。
例)外部接続のHDDやSSDなど。 - 保存電子期間帳簿は、作成した日から7年間保存することが法律で義務付けられています。
- 保存形式は、PDF形式やCSV形式での保存法が一般的で、その保存形式に関しては各企業及び個人事業主が決めることが出来ます。
但し、データ改ざんなどが無いか確認するために、電子署名やタイムスタンプを確認できるようにしておく必要があるので注意してください。
これらの要件を満たした保存方法で保管期間満了まで、しっかり保存することで、脱税を根絶して税負担の公平性を担保出来ることが求められています。
(開業前に知っておきたい帳簿のつけかた)は
amazon.co.jpを宣伝しリンクすることでサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラム、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。