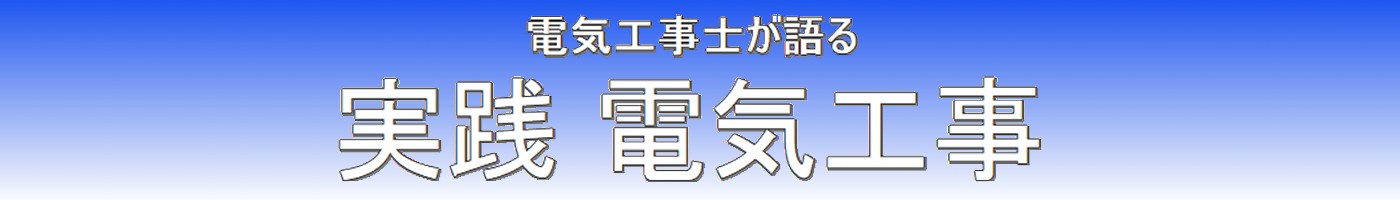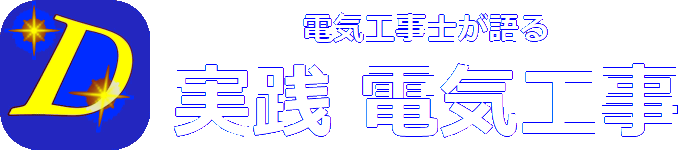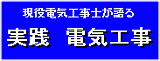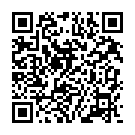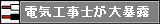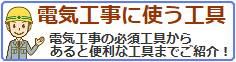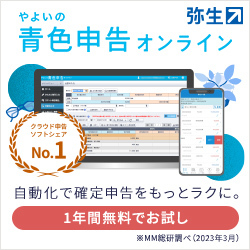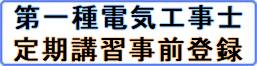銅板埋込接地工事について
電気工事において接地工事が大切なことは、電気工事士の方なら誰しもが認識しているところで、日々いろんな現場で接地工事を行っておられることと思います。
一般家庭のように洗濯機や電子レンジ、冷蔵庫、ウォシュレットなどの家電品に用いるD種接地工事程度なら、簡単ですが、A〜C種接地工事となると、求められる値も厳しくなるので、求められる値まで下げるのに苦労されている電気工事士さんも多いんじゃないかと思います。
私も、いろんな現場で電気工事を行う中で、数多く接地工事を行ってきましたので、中には、どうしても基準値まで下らず苦労することも一度や二度ではありませんでした。
というか、今でも苦労することがあるのが現状です。
私が行う電気工事の中で行う接地工事でよく行うのが
【打込み工法】と呼ばれる連結式アース棒を地面に打込むだけの単純な接地工法です。
この工法は、施工が簡単なので、多くの現場で用いられている工法で、規模の小さなキューピクル接地工事や小型の電気室などの施工時によく行われている工法なので、みなさんの中にもこの工法で施工されたことがある方も少なくないと思いますし、材料費も比較的安価なので、電気容量の多い一般住宅や学生向けワンルームマンションなどでも用いられることがあると思います。
この【打込み工法】の利点は、今挙げたようなことが言えますが、デメリットとしては、打込み場所の条件が悪いと中々値が下らないという事があり、一旦値が下らなくなると、場所を変えて打込んで、それらを連結するとい作業が増えてしまうことが少なくありません。
それも2、3箇所ならいいですが、それ以上となることも少なくなく、打込み範囲が広範囲に及ぶこともあるのが、ネックとなることもあります。
詳しい施工方法や打ち込みアース棒などの参考資料として、下記サイトの関連ページを掲載しておきます。
そんなデメリットが比較的少ないのが、今回ご紹介する銅板埋込工法による接地工事です。
用いる銅板は、一辺が600mmもしくは900mmの正方形の銅板に取り出し用リード線が付いたものになります。
簡単なイラストにするとこんな感じです。
これを地面に埋めることで、広い接地面を得ることが出来るので、より効率的に対地アースを取ることが出来ます。
ごく簡単に逝ってしまえばこうなるのですが、これではタイトルにした
『銅板埋込接地工事について』の内容としては、あまりにも不親切ですので、次に施工手順をご紹介しておきますので、実際に現場での施工にご活用ください。
銅板接地工法施工手順
- 最初に銅板埋設位置を選定します。
- 選定場所に銅板埋設用穴を掘削します。
- 掘削穴に銅板を設置します。
銅板は、水平もしくは垂直に設置し、水平、垂直に関しては、現場の状況等で判断してください。
- 接地抵抗計を接続して設置抵抗値の測定します。規定値まで下るように接地極を追加します。
- 規定値以下でない場合、接地極を追加して再度測定します。
- 設置抵抗値が規定値以下であることを確認し、リード線に建物への取り込み用アース線を接続して建物に取り込めるようにします。
これで銅板埋込接地工事はひとまず終わりです。
関連ページとして下記にページリンクを掲載しておきますのでご覧ください。
こちらのページで銅板敷設に必要な材料の確認も行えるので、現場施工の前に確認すると必要な材料の選定にも役立ちます。
ここで、銅板埋込場所の選定に関して、覚えておくべき項目を挙げておきますので設置場所選定の参考にしてください。
銅板埋込場所は電気設備の近くで、土壌が湿っている場所を選ぶようにしてください。
接地極は、適度な湿り気がある方が、地絡電流を逃がしやすく、測定時にも規定値を得やすくなります。
銅板埋込時の掘削深さは、1.5m〜2.0mというのが一般的ですが、地質や地盤の状況により、掘削深さは変わってきます。
また、接地極を複数敷設する場合は、さらに掘削深さが必要になるので、注意してください。
接地極の離間距離
今回は銅板埋込工法の説明をさせていただいていますが、ご存知のように接地極として用いられるものには、銅板のほかに、銅棒、鋼棒などがあるのは、みなさんご存知だと思います。
今回紹介している銅板を埋設する方法での各接地極の離間距離は、各々1mとされています。
因みに銅棒の場合は、0.5m、鋼棒では、0.25mとなっています。
最後に『接地極埋設標』の設置を求められることもあるので、予め用意しておくことをお勧めします。
接地極埋設標 (黄銅製)
令和 国土交通省仕様 刻印タイプ
使用する接地極によって離間距離も違うので、施工現場で間違わないようにすることが求められるので、このページをスマホ等で簡単に確認できるようにブックマークしておいていただくと便利だと思います。
何とも押しつけがましい書き方になってしまいましたけど、実際、現場でこれらのことを一々調べるのも面倒なので、私も参考にできる資料やWebサイトをブックマークして利用させていただいていますので、私のサイトが現場での一助としていただければと思っていますので、みなさんの現場作業にご活用ください。
m(_ _ m)
スポンサーリンク
(実践 電気工事)は
amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムであるAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。