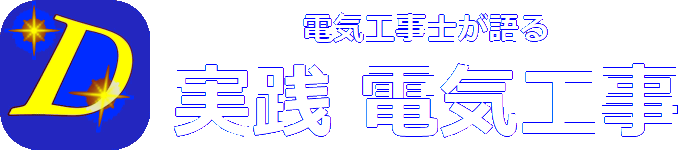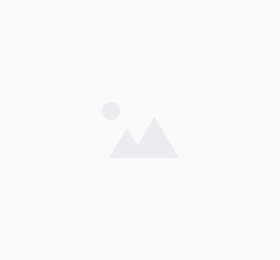スポンサーリンク
サイト内に一部広告が含まれています。
フルハーネス型安全帯使用特別教育
フルハーネス型安全帯完全義務化に伴う特別教育の実施と受講に関する情報を紹介してあるので、現場で高所作業をする人は、必ず受講するようにしてください。
これまでは、胴ベルト型安全帯からフルハーネス型安全帯への移行期間でしたので両方使えましたが、今後はフルハーネル型安全帯が完全義務化され、一定高さ以下の特別な条件以外は、原則フルハーネス型安全帯の着用が義務付けられることになります。
これに伴って、厚生労働省から「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が公表され、その中で労働安全衛生規則に規定されている特別教育規程関係に基づいて、フルハーネス型安全帯使用に関する特別教育の実施が記されていることから、フルハーネス型安全帯を使用する人は必ず特別教育を受けなくてはなりません。
このページにフルハーネス型安全帯使用に関する特別教育の情報を掲載しておきます。
墜落制止用器具の安全使用改正点
厚生労働省から公表されている「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に関するこれまでのものからの改正点は、大まかに次の3項目です。
- 「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更する。
- 「フルハーネス型安全帯」の着用が義務化される。
- 特別教育受講が義務化される。
1. 墜落制止用器具とは
「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更されましたが、法律的な呼び名が変わっただけで、通称として「安全帯」を使うことに問題はありません。
但し、電柱などで使用されてきた胴ベルト型(U字つり)は、墜落を制止する機能がないので上記の「墜落制止用器具」から外されることになり、今後は「ワークポジショニング器具」と呼ばれるようになります。
「ワークポジショニング器具」を使用する際は、「墜落制止用器具」を併用しなくてはならないので注意してください。
フルハーネス型安全帯着用義務化
現行規格品は、2022年1月2日以降使用禁止となりその後はフルハーネス型安全帯の使用が完全義務化されます。
但し、6.75m以下(建設業は5m以下)では、これまでどうり胴ベルト型ランヤードの使用も可能です。
逆に6.75m以下(建設業は5m以下)でフルハーネス型安全帯を使用すると落下距離が長く、地面にとどく可能性があるので、使用するときはD環取付位置を高い所にするなどの対策が必要になります。
特別教育受講の義務化
高さが2m以上nの所で作業床を設けることが困難で、フルハーネス型安全帯を使用する作を行う作業者は「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を受けなくてはならない。
6.75m以下(建設業は5m以下)で作業し、フルハーネス型安全帯を使用しないものは、「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を受ける必要はない。
しかし、実際の現場でこのような作業状況は考えにくいので、ほぼすべての作業員が特別教育の対象となると考えるべきです。
フルハーネス型安全帯使用特別教育内容
|
科目 |
範囲 |
時間 |
|---|---|---|
|
|
60分 |
|
|
120分 |
|
|
60分 |
|
|
30分 |
|
|
90分 |
受講時間は、合計6時間になります。
但し、一定条件を満たすものは、一部受講を省略できます。
- フルハーネス型安全帯使用作業 6月以上経験者
1) ・2) ・5)省略可 - 胴ベルト型墜落制止用器具使用作業 6月以上経験者
1)省略可 - 「ロープ高所作業特別教育受講者」または「足場の組立て等特別教育受講者」
3)省略可
フルハーネス型安全帯使用特別教育実施機関
この特別教育は原則、事業主が作業者に対して行うことになっているものですが、多くは次の機関が行うものを受講するのが一般的です。
以前は、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の助成対象になっていましたが、既に助成金交付期間が満了したので、現在補助や助成対象ではありませんが、何か他の助成制度があるかもしれないので、建設業労働災害防止協会に問い合わせてみるのもいいでしょうし、国からの助成事業は多々あるので、他に利用できるものが始まっているかもしれませんので、一度調べてみるべきだと思います。
その時に役立ちそうなページを紹介しておきますので、参考にしてください。
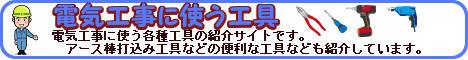
スポンサーリンク