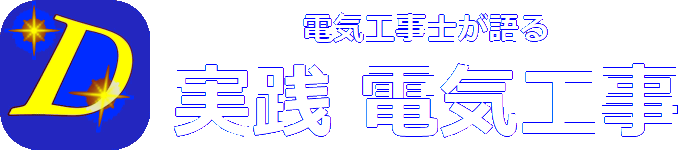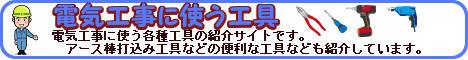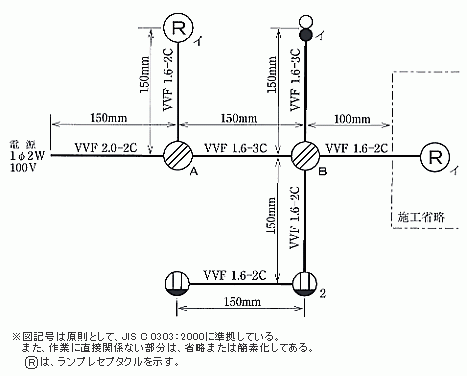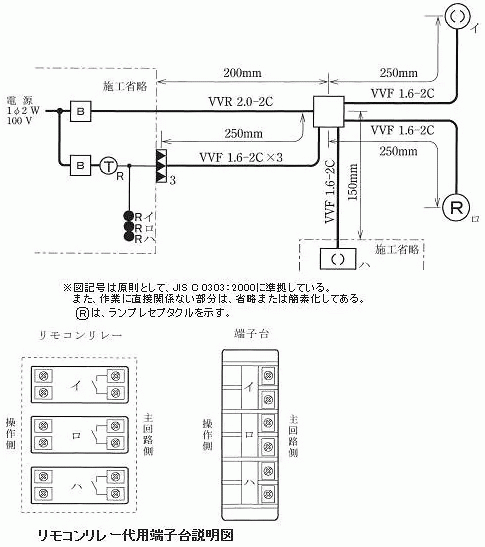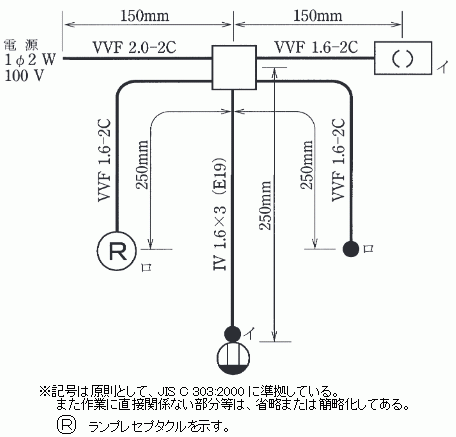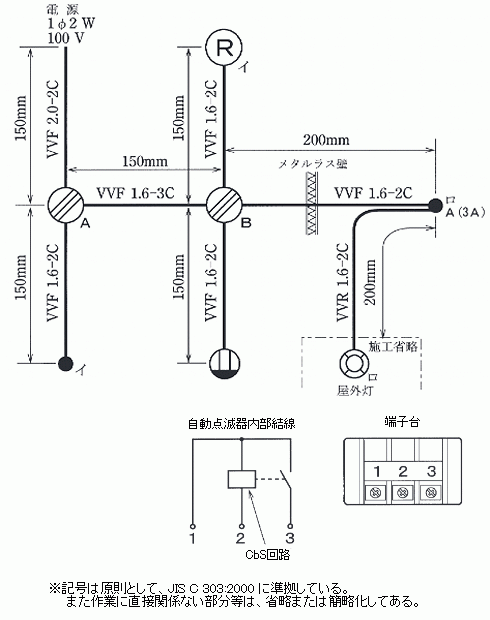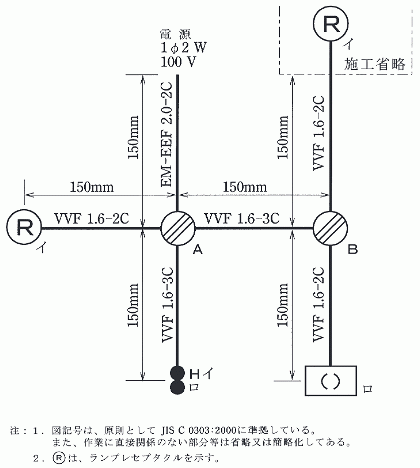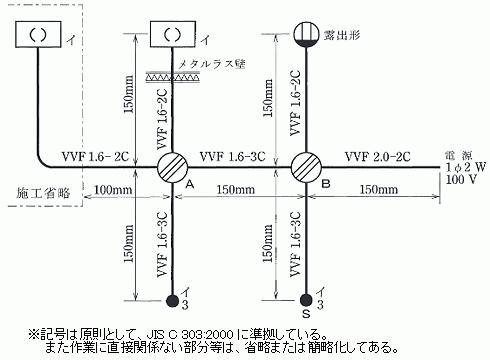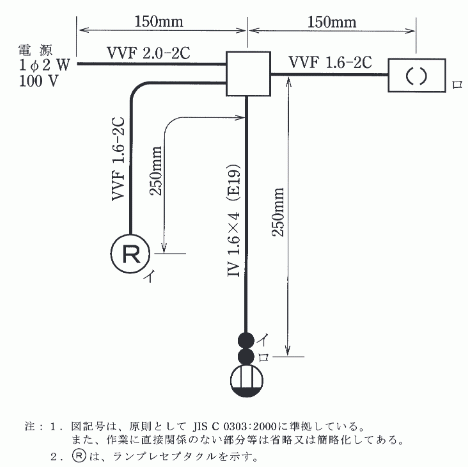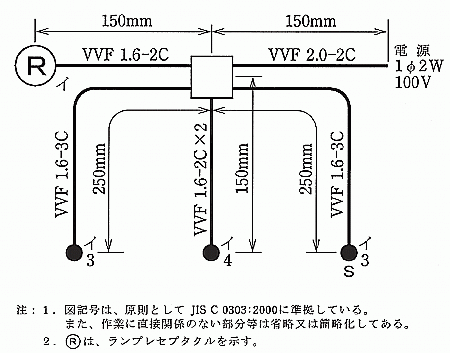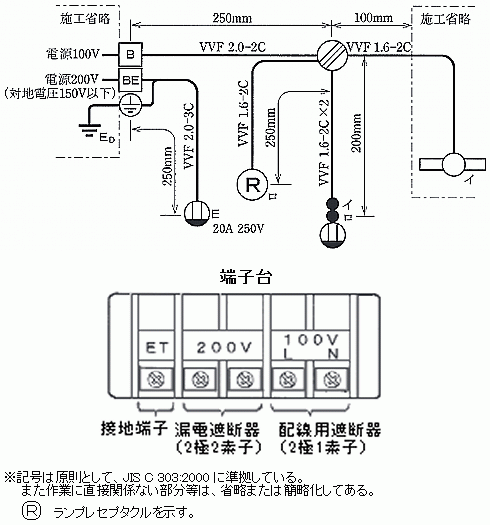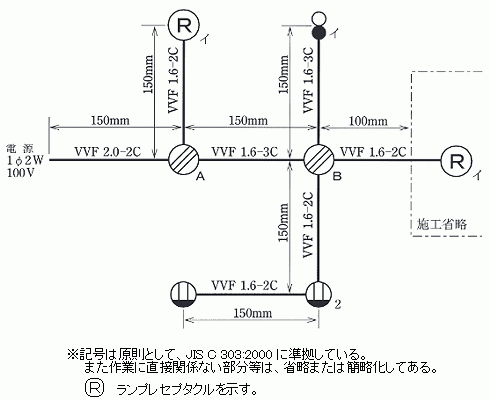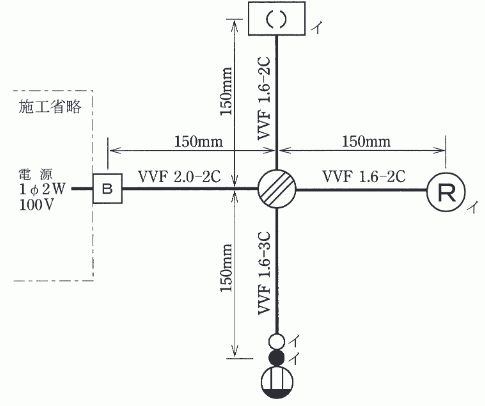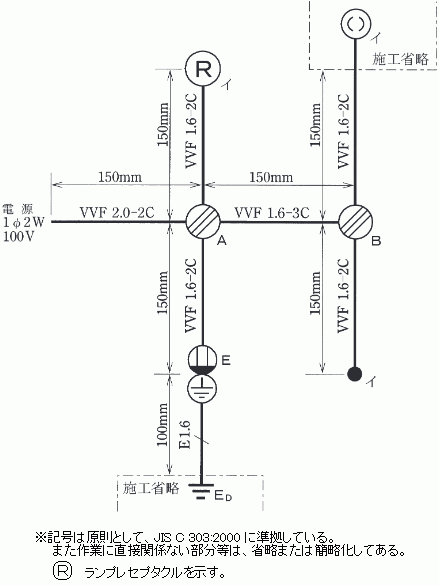スポンサーリンク
サイト内に一部広告が含まれています。
第二種電気工事士技能試験施工例
第二種電気工事士技能試験受験における過去の回答複線図です。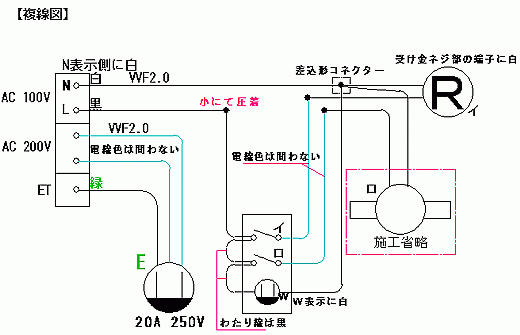
解説
AC100/200V接続部分は、端子台にて接続し、照明器具(レセプタクル及び施工省略部分)2台に対して、各スイッチを設ける。
スイッチ部分にコンセントも設け、その回路は、照明器具と同一回路とする。
AC200V回路には接地極付200V用コンセントを接続する。
差込形コネクター以外のジョイントは、全てリングスリーブによる圧着とする。
AC100V(L:黒)側は、リングスリーブ(小)を用い、圧着工具(小)の刻印表示にて圧着する。
スイッチより照明器具へ至る電線は、リングスリーブ(小)を用い、((○ )の刻印表示にて圧着する。
この圧着を間違うと不合格となる。
尚、上記複線図は、一例であり、施工条件及び電気的に正しく結線されていれば、他の結線方法でも正解とされる。
結線順序
今まで電気工事を行ったことが無く、初めて結線を行う時、ほとんどの方が電線の本数を見て悩まれます。
しかし、電気の基本を思い出していただければ、簡単だと思います。
電気は、プラスとマイナスの二つの電極から成り立っています。
つまり、最終的にはこの二本さえ間違わなければ、問題ないという事です。
複数の電線の結線について、具体的に解説しましょう。
上図の電灯回路の結線を例にすると、
電源(AC100V)から電源線(VVF2.0)の電線が取り出されています。
その電源に対して、負荷(照明器具2台とコンセント)が接続され、その照明器具2台にそれぞれスイッチを設けるようになっています。
結線手順
- 接続電線を仕分ける
- 接続電線を接続系統ごとに一まとめにして、各接続ごとに分けてください。
- 接続本数の多いものから接続する
- 上図の例では、N極(マイナス)の接続から行います。
- 負荷側(照明器具2台、コンセント)のそれぞれ白(マイナス)側を接続します。
- 照明分2本、コンセント分1本、そして電源分の計4本となります。
- スイッチ回路を接続する
- 照明器具(イ) (ロ)それぞれのスイッチ線と照明器具側の黒線をそれぞれ接続してください。
- L極側(プラス)を接続する。
- 最後に、L極側(プラス)をスイッチ線と接続してください。
これで、全ての結線は終了です。
電線をまとめるときに使うと便利なものに、
ホーザン(HOZAN)の合格クリップというのがあるので、
技能試験を突破できるよう紹介しておきます。
ホーザン(HOZAN) 合格クリップ
この合格クリップを使って接続する電線をひとまとめにしてから接続すると、間違う確率も下がるし、しっかり接続できます。
まず最初に、接続電線本数の多いものから接続する事で、後々間違いがあっても気付きやすくなります。
そして、一つ一つ確認しながら接続を行う事で結線ミスを防ぐことになります。
これは、実際の電気工事の現場でも大切なことなので、この段階で、身に付けておいてください。
実際の電気工事の現場では、一つの結線ミスが重大事故にもつながるので、確実な作業が要求されます。
(この手順は、私が実際の現場で行っているもので、みなさんに強制するものではありません)
![]()
PDF形式ファイルを見るには、Adobe Acrobat Readeが必要。
取得していない方は、上記アイコンをクリックし、ダウンロード(無償)してください。
スポンサーリンク